はじめに:XRPは終わったのか? それともこれから本領発揮か?
「XRPはもう古い」「リップラーは時代遅れ」――そんな声が2022〜23年頃にはSNSでも頻繁に聞かれました。
しかし2024年にSEC(米証券取引委員会)との裁判が一定の和解を迎え、XRPの存在感は再び増してきています。
私自身、2020年頃からXRPを保有しており、訴訟中も買い増しを続けてきました。今回は個人投資家の視点で、XRPの将来性・リスク・注目ポイント、そして私の戦略までを解説していきます。
XRPの基本:なぜ世界中の金融機関が注目してきたのか?
▶︎ ブロックチェーン界の「Swift代替」を目指した通貨
XRPは、Ripple社によって開発された国際送金向けの仮想通貨。特筆すべきは、以下の2点です。
- 送金速度:約3〜5秒(BTCやETHの数十分〜数時間とは圧倒的な差)
- 送金コスト:数円レベル(国際送金では革命的な低コスト)
この仕組みにより、世界中の銀行・送金業者が注目する存在となりました。特に日本ではSBIグループがRipple社と連携しており、リップラー(XRP愛好者)も多いですね。
裁判の決着:SECとの和解が与えたインパクト
2020年から続いたSEC(アメリカ証券取引委員会)との訴訟問題は、XRPの将来性に大きな影を落としていました。
しかし2023年〜2024年にかけて、以下のような進展がありました:
- 一部訴訟は和解
- XRPは証券ではないとする判決(一定条件下)
- アメリカの取引所(Coinbaseなど)でもXRPが再上場
この一連の動きにより、「規制の壁」が崩れつつあります。
私はこのタイミングで、XRPを積極的にポートフォリオに組み直しました。
現状のユースケースと今後の実用拡大
▶︎ ODL(オンデマンド流動性)による実需の拡大
RippleNetという決済ネットワークの中で、XRPは国際送金の中継通貨として使われています。特にODL(On-Demand Liquidity)というソリューションが世界中で導入されています。
2025年現在では、以下のような国・銀行・決済事業者がRippleNetに参加中:
- SBIレミット(日本)
- Santander銀行(スペイン)
- Tranglo(マレーシア)
- Pyypl(中東)
これにより、XRPの取引量や流動性は年々増加傾向。投機目的だけではなく、実需としての役割が増している点は他の仮想通貨と一線を画しています。
今後の可能性:XRPが担うかもしれない「次世代送金インフラ」
私がXRPに注目し続けている最大の理由は、「法定通貨とブロックチェーンの架け橋になれる存在」だからです。
▶︎ CBDC(中央銀行デジタル通貨)との統合
Ripple社はCBDC向けの専用プラットフォームを開発しており、複数の国と提携中です。
例:
- ブータン王国:中央銀行がRippleと提携
- パラオ共和国:デジタル通貨発行にRipple技術を活用
将来的には、日本円・米ドル・ユーロなどのCBDCと、XRPを使った国際交換が可能になる可能性があります。
✅ ポイント:
- XRPはグローバル送金の「中立通貨」になれる
- 銀行とも連携できる“数少ないブロックチェーン資産”
このようなポジションを築けているのは、他にETHやXLMくらいです。
XRPの懸念点・リスク
どんな資産にもリスクはあります。XRPにおいても以下の点は注視が必要です。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 中央集権性 | Ripple社による発行・管理が強く「分散性」に欠けるという批判あり |
| 今後の規制 | 米国以外でも金融規制が強化されれば、新たな障壁になる可能性 |
| 競合の台頭 | Stellar(XLM)やSWIFTのブロックチェーン化など、競争が激化中 |
私自身、「リスクを承知の上で戦略的に保有する」ことが重要だと感じています。
私のXRP投資戦略(2025年最新版)
個人投資家の1人としての見解ですが、短期で利益を狙うならば保有しても良いと思っています。
ビットコインと比較すると長期保有には不向きかと思います。
本来は送金を目的とした通貨になりますので、本来の役割を理解した上で購入するのならば良いでしょう。


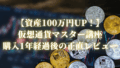
コメント